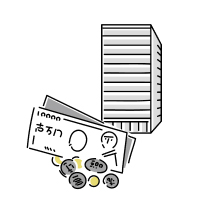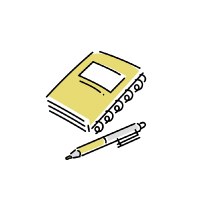■ 言うまでもなく,夫婦関係について弁護士のところに相談に来られる方は,「離婚したいけれどどうすればよいか」という内容がほとんどです。
しかし,もちろん中には「配偶者から離婚を求められているが自分は修復したい。どうすればよいか」という相談もあります。
■ 正直申し上げて,弁護士というのは,離婚する場合に生じる親権・財産分与・慰謝料等の種々の問題について解決する手段を提案することはできても,破綻した(あるいは破綻しかかっている)夫婦の関係を修復する「法的解決方法」を持ち合わせていません。
もちろん,形式的に調停を申し立てて,調停に同行させていただく,というレベルでのお手伝いはできますが,一度離れてしまった相手方の気持ちをこちらに取り戻す,というような「天使」のような役割は到底果たせません。
■ 他方で,弁護士は,多かれ少なかれ「説得」の技術を持ち合わせています。
「気持ち」を変えることはできなくとも,(嫌な言い方ですが)離婚に伴う社会的・経済的な不利益を主張することにより,相手方の「離婚したい」という「決意」を鈍らせることはできるかもしれません。
そして,仮に,一時的に「決意」が鈍り,時間をかせぐことができれば,「気持ち」の変化をもたらすチャンスは増えるように思います。
■ 私自身,よく「関係を修復したい」というご相談を受けることがあります。そのような場合には,「法的専門を離れたあくまで一個人の意見」として,過去の様々な事例から破綻した夫婦の問題点などを(もちろん守秘義務に反しない範囲で抽象化してですが),お話し,修復に向けた話し合いの「ポイント」を助言することはあります。
このような場合,ほとんどは相談だけに終わることが多いので,どこまで役に立っているが検証は困難ですが,何も聞かないよりましかもしれません。
■ 医療過誤訴訟にカルテは不可欠
医療過誤など医療に関する責任追及には,当該患者の医療記録(カルテ)の検討が不可欠となります。
医療過誤訴訟を提起する場合,裁判所より必ずカルテの提出を求められます。
カルテについては,患者(あるいは遺族)が,病院に対して任意に開示を求めることができます。原則として,病院はこれを拒否することはできません。
■ カルテの収集方法
具体的な収集方法ですが,病院に申し込むとコピーをして渡してくれるところもあります。この場合,実費として,カルテ1枚につきコピー代10~30円を徴収されることが多いようです。
また,これも病院によりますが,カルテの開示だけを受けて,それを当該病院の一室で自分でコピーしなければならない場合もあります。
コピー機がないような病院で,しかもカルテ自体の貸出を認めない場合には,デジタルカメラを持って行き,その場で撮影する場合もあります。
いずれにしても病院によって対応が異なりますので,事前によく確認してください。
■ カルテの証拠保全について
カルテが開示前に改ざんされることを危惧して,証拠保全という手続を行うことがあります。
これは,裁判所に申し立てて,日程を調整し,事前に病院に知らせることなく,ある日突然に,裁判官,書記官,代理人らで当該病院を訪れ,カルテを開示させるものです。
基本的に病院はこれを拒否できませんので,事前の改ざんの危険性が減少します。
但し,申立さえすれば簡単に認められるというものでもなく,裁判所に対し,ある程度具体的に,医療過誤等の内容を書面で説明する必要があります。
このような作業は,専門家である弁護士に依頼したほうがスムーズです。
■ いわゆる電子カルテについて
かつては,手書きのカルテが多く,証拠保全をする場合でも,改ざんの痕跡がないかを,現場でかなり細かくチェックする必要がありました。
しかし,最近はいわゆる電子カルテが増え,改ざんの危険性はかなり減少したように思います。
大きな病院にある一般的な電子カルテのシステムでは,一度入力したものは,書き直しても原則として消えません(通常,当該箇所に線が引かれ訂正したことが分かるようになっています)。
また,入力する際には,職員個々人が持つID番号を入力しなければならないことになっており,誰が入力・訂正したかも明らかになります。
確かに,このシステム自体を不正に書き換えるということも理論的には考えられないことはないですが,そのようなことをするためには,システム自体を作成した業者の協力が必要となる可能性が高く,そのようなリスクを冒す業者がいる可能性は低いのではないでしょうか。
従って,電子カルテ自体については証拠保全の必要性はそれほど高くないようにも思います。
■ 手書きの書類について
ただ,電子カルテが導入されている病院でも,患者本人の同意書などは手書きされたものをスキャナーで読み込んでいる場合が多く,その同意書自体に疑義があるような場合には,その原本を確認する必要があります。
この意味では,電子カルテのシステムを導入している病院においても,証拠保全の必要性はあると思います。
■ お気軽にご相談を
いずれにしても,どの方法を採るかはケースによって異なります。お気軽にご相談ください。
但し,入手したカルテを元に損害賠償請求を求める場合には,さらに専門的な検討が必要となり,その場合には協力していただける医師の存在が不可欠となります。
■以前に別項で,夫のモラルハラスメントについて触れましたが,少し前に私が扱った事件で,「モラハラ」を理由とした比較的高額の慰謝料が認められました。
■この事件でも,夫は,自分が絶対正しいと思いこんでいて,その考えを曲げようとしませんでした。そして,一度口論になると,長期間,妻を無視するのです。
妻は,長年,なぜこのような仕打ちを受けるのか,自分が間違っているのか,と悩み続けました。
しかし,ある公的な相談窓口において,夫の行為が典型的な「モラハラ」であることを知るに至り,離婚を決意し当職に相談に来られました。
■訴訟においても,夫は,決して自分の主張を曲げなかったことから長期化しましたが,慰謝料自体が減額されることはありませんでした。
夫の不貞という事情もない中では,かなり高額な慰謝料であったと思います。
裁判所にも,単なる「性格の不一致」とは異なる,一方配偶者による「モラハラ」が違法なものであるという理解が徐々にですが広まってきているのではないでしょうか。
■もし夫婦関係で悩まれており離婚を考えているものの,「自分にも問題があるのでは」などと思いこんでおられる方がおられましたら,一度ご相談ください。
弁護士である以上,法的な解決手段しかご提案できませんが,一定の範囲で同様の事例をご紹介しアドバイスさせていただきます。
■皆さんから離婚事件の相談を受けるにあたって,いつも心がけていることがあります。それは,①法律家としてのアドバイスと,②法律家を離れた個人としてのアドバイスを,相談者に分かるように分けて説明することです。
■弁護士としての意見
これは,すでに離婚を決めておられる方が,配偶者や,あるいは不貞相手に対し,どのような法的手段を採ることができるか,を説明することです。
婚姻中であれば婚姻費用の請求ができること,不貞相手に対しては慰謝料の請求ができること,過去の事例に照らしてどれくらいの金額が請求できるか,などです。
■個人としてのアドバイス
ただ,相談に来られる方(女性が多いですが)が,きちんと気持ちを整理して方針を確定させていることはそれほど多くありません。
当然のことながら,長い時間をかけて,全人格的な結びつきを目指した婚姻生活を終わらせようかと考えているのですから,単純にお金の問題だけに置き換えることは困難なことが多いのです。
そのような場合に,安易に「それは離婚したほうがよいですよ」とか,「離婚したら経済的に大変ですよ」とか言うことはできません。
ただ,相談者は,弁護士のことを「専門家」と見ておられることが多いですから,そのような意見ですら「従ったほうがよいのかも」と思いがちです。
■弁護士は法律の専門家に過ぎません。
私たち弁護士は,法律については国家的な資格に基礎付けられた専門的な知識を持っていますが,それ以外のことについては基本的に素人なのです。
もちろん,同種の事件を数多く扱うことによって,法律以外の知識が蓄積されることもありますが,多くの場合,弁護士資格のように,そのことを客観的に証明することはできません。
■そこで,私は離婚の相談を受けた場合には,「あなたが離婚しようと決めた時にはこのような法的手段があります。ただ,離婚したほうがよいかどうか,不貞相手に請求するかどうかについては,お気持ちの問題もあり,弁護士としてはアドバイスすることはできません。ただ,あくまで私個人の意見として申し上げるなら~」として,法的なアドバイスかどうかをきちんと分けて説明するようにしています。
■もちろん,そもそも弁護士がそのような個人としてのアドバイスをすべきではない,という意見もあるでしょう。
しかし,現実に,離婚問題で憔悴しておられる相談者を目の前にすると,例えば,「どんな複雑に見える離婚事件も必ず終わりましたよ」とか,「とりあえず今すぐに決めずに,しばらく何も考えずにゆっくりされてはどうですか」などと言うことがあります。
■いずれにしても,弁護士にとっては多くの事件の一つであったとしても,相談に来られる方にとっては,人生の一大事である,ということを常に意識しながら,ご相談をお聞きするように心がけています。
◆ 近ごろ、親の遺産相続をめぐって、兄弟姉妹の間で紛争になるケースの相談をよく受けます。
身内のもめごとは、他人同士の紛争よりやっかいです。
両親のどちらかが存命のときは、あまりもめなくても、二人とも亡くなってしまうと、よくもめることがあります。
◆ 遺産分割協議が円満にまとまることもあります。まとまらないときは、家庭裁判所の調停で解決することになります。
調停は話合いですから、調停がまとまらないときは、家庭裁判所の審判という裁判手続で、裁判官が決定することになります。
◆ 親の立場からすると、自分の死亡後に、子らが遺産相続をめぐって、紛争にならないようにしたいものです。
一番良い方法は、親が元気な間に、遺言書を作っておくことです。そして、その内容を子どもたちに説明しておくことだと思います。
◆ 遺言書は、自分で作成することができます(これを自筆証書遺言といいます)。ただし、全文を自署し、日付及び氏名も自署し、印鑑を押さなければなりません。ワープロで作った遺言書は無効です。
◆ 遺言書を確実に作ろうと思えば、公正証書遺言がおすすめです。
これは原案を作り、公証人(元裁判官や元検察官)の役場に持参して、公正証書に作ってもらうものです。原案を作るときは、弁護士に相談したり、遺言執行人を弁護士に指定しておくということもできます。
◆ ただ、親や子どもは、遺留分といって、一定の相続分を受取る権利があります。親だけが相続人のときは、全体の遺産の3分の1、配偶者や子どもが相続人のときは全体の遺産の2分の1です。
できれば、これらも考慮して遺言書を作っておくことが、家族の紛争の予防になるでしょう。
■ 司法書士が、抵当権抹消登記の際、本人意思の確認をしなかったとして、損害賠償請求された事件で、司法書士に責任がなかったとして勝訴しました。私は、司法書士側の代理人です。
■ 原告(女性)は、息子の友人の社長が経営する不動産会社に5億円を貸付け、不動産会社の土地に抵当権を設定しました。数年後に、社長は、新たに別の金融会社に融資を頼みました。新たな融資を受けるためには、最初の抵当権を抹消する必要がありました。
被告の司法書士は、金融会社から頼まれて、原告の抵当権抹消と新たな融資に伴う金融会社の抵当権設定の二つの登記を依頼されました。
司法書士は、原告(抵当権抹消の当事者本人になる)が取引当日に取引場所である金融会社に来るものと思い、その場で直接、登記意思を確認しようと思っていました。
ところが、取引場所には、社長とその友人である原告の息子しか来ず、原告は来ませんでした。しかし、社長と息子は、原告の委任状と抵当権の権利証(登記済み証)を持参しました。そして、原告は急用で来れなくなった、と説明しました。
司法書士は、原告の意思を直接、確認出来ず、不安がありました。しかし、社長及び原告の息子とは、初対面ではなく、以前に登記取引をしたことがあったので、2人を信頼して、抵当権抹消登記をしました。数年後、不動産会社は倒産し、社長と息子は行方不明となりました。
不動産会社倒産後、原告は、抵当権が抹消されていることに気付きました。原告は、権利証は社長と息子が、無断で原告の自宅から持出したものであり、委任状は偽造されたと主張し、司法書士と金融会社に対し、5億円の損害を被ったとして、その損害の内金8千万円の損害賠償請求を大阪地裁に起こしました。
■ 司法書士が登記をする場合、原則として本人意思を確認する義務があります。しかし、登記の迅速性の要求との兼ね合いで、どのような場合に、本人意思確認を怠ったとして、損害賠償責任があるかについては、責任を認めた判例や、否定した判例があり、裁判所の判断が分かれています。専門家責任訴訟の一分野です。最近の司法改革で、司法書士の権限が拡大されましたので、その責任が厳しく問われる傾向があります。
■ 私は、司法書士の代理人として、権利証と委任状が持参されたことなどを強調して、原告の意思を疑う事情がなかったので、司法書士に責任はないことを強く主張しました。
果たして、大阪地裁の判決は、司法書士の主張を採用し、原告の請求を棄却しました。その理由は、司法書士は、社長やその友人と以前から面識があったこと、その友人は原告の親族に当たるとの説明を登記前に受けたこと、権利証と委任状が持参されたことなどから、原告の登記意思を疑うに足りる事情はなかったとし、原告の意思を直接、確認するまでの義務はなかったとしました。
■ 原告は控訴しました。司法書士は高裁でも勝訴の展望はありましたが、裁判所から和解勧告もありましたので、地裁の勝訴判決を前提にして、少額の解決金を支払うことで和解解決しました。
■ 被告とされた司法書士は、「勝てると思っていたが、地裁で全面勝訴判決が取れて、うれしかった。そのうえ、高裁でわずかな解決金の支払いで解決して本当に良かった。」と喜んでおられました。
私も勝利的解決が出来てとても良かったと思いました。
■ これまで何件もセクシャル・ハラスメントが問題となる事件を扱ってきました。
犯罪になりかねない極端な事案は別として,現実には,セクシャル・ハラスメントかどうかの判断は難しいもので,裁判官によっても判断が揺れるように思います。
■ 依頼者のプライバシーの問題がありますので詳細は避けますが,かなり以前に,次のような事案を扱ったことがあります。
社員が20名くらいの小さな出版会社で,入社したばかりの女性社員に対し,社長が,歓迎会と称してバーに誘いました。
1対1で社長と出かけるのは気が進みませんでしたが,希望に溢れて入社したその女性は,社長の誘いを断ることができませんでした。
バーでは,酔ってきた社長が肩に手を回してきたり,「彼氏はいるの?」などと聞いてくるようになりました。他方で,そのような話や態度の合間に仕事の話しもすることから,女性は,なかなか退席できませんでした。そのような状況の中,さらに酒に酔った社長は,調子にのって,女性にキスを求めてきたのです。
女性は嫌でたまりませんでしたが,入社したばかりで社長の指示を断ることが出来ず,軽くキスをしてしまいました。
帰宅した女性は,大きな後悔と嫌悪感にさいなまれ,これからは仕事に専念し,社長の誘いがあっても必ず断ることを決心し,翌日からの仕事に臨みました。
社長は翌日からも,調子に乗って飲みに誘ったりしてきましたが,女性はこれを断り続けました。すると,社長は態度を急変させ,「仕事がきちんとできない」などと難癖をつけ,入社から僅か1ヶ月程度で女性を退職に追い込んだのです。
■ 女性は,意を決して訴訟を提起しました。
ところが,一審では,「キスは女性が自分の意思で応じたのだからセクハラではない」という理由で敗訴したのです。女性は大変傷つきましたが,どうしても納得がいかず,控訴しました。
控訴審は年配の3名の男性裁判官が担当しました。尋問においても,「嫌なら断れたのではないの?」などと聞いてきたことから,私は,これでは難しいかも,と思ったのですが,驚いたことに,和解の席で,裁判官は「キスをさせたことがセクシャル・ハラスメントであったことを前提に和解を勧告します」と述べたのです。その結果,相手に相当の慰謝料を支払わせることができました。
■ このように,指揮監督関係がある中でのセクシャル・ハラスメントについては,裁判官によって対応が違うことがよくあるように思います。
また,必ずしも女性の裁判官が理解してくれるというわけでもないように思います。
「嫌なら断れるでしょう」
このように述べる女性裁判官に会ったことがあります。
しかし,男性の私が言うのも変ですが,働かなければならない女性にとって,指揮監督関係に基づく心理的な圧力は,(想像するしかないのですが)大変大きなものであると思います。多くの女性労働者が,「いやだな」と思っても,笑顔で上司の言動に対応せざるを得ない経験をお持ちだと思います。
従って,事件処理においても,単純に,こちらの受けた被害を並べるだけではなく,「なぜ断ることが出来なかったのか」という客観的な事情を工夫して主張し,裁判所に理解してもらう必要があります。
■ いずれしても,そのような被害にあった依頼者に対しては,私自身が男性であって,限界があることをいつも肝に銘じながらも,出来るだけ依頼者の心情を理解するように努めたいと思っています。
○ 平成25年8月、大阪市梅田のガールズバーで、料金不足をめぐる客と店長のトラブルから、店長が2階から1階に階段を転落して死亡する事件がありました。この件で客(35歳、会社員)が殺人未遂(その後殺人に切換え)で、曽根崎署に逮捕されました。私が国選弁護人として弁護活動をしました。弁護の成果があり、無実を明らかにできました。その結果、検察官の不起訴処分を得られ、会社員は釈放されました。
その事件について紹介します。
○ ガールズバーで、会社員は、料金4,900円を請求されましたが、所持金は3,300円しかありませんでした。すると、店長は、いきなり、会社員のカバンから、携帯電話と運転免許証入りの財布を取り上げました。会社員は、それを取り返そうとしました。店内で二人がもみ合いとなりました。会社員は、店長から投げ倒されたので、こわくなり、2階入り口ドアを開けて、逃げようとしました。店長は、会社員を逃がすまいとして、背中をつかみました。二人はもみ合って、一緒に、2階から1階へ階段を転落しました。店長は、1階のコンクリート壁に頭を打ち付け、頭蓋骨骨折等の重傷を負いました。会社員は、背中に擦過傷を負っただけでした。会社員は、店長が倒れているのを見て、通行人に救急車の手配を頼みました。その後、駆け付けた警察官に逮捕されました。この事件で曽根崎署は、殺人未遂罪で会社員を逮捕しました。
○ 私は、事件直後、会社員の両親から相談を受けました、そこで、法テラスの国選弁護人として、他の弁護士1名と一緒に、弁護活動をしました。勾留半ばに店長が意識不明のまま死亡したので、事件は殺人罪に切り換えられました。
会社員から事情をよく聞くと、わずか数千円の料金不足で、店長を殺すような意図がないことが、はっきりしました。店長が死亡した結果は重大ですが、実際は二人が一緒に転落した事故だと思われました。
そこで、弁護活動としては、曽根崎署に勾留されている会社員に、ほとんど連日、接見(面会)し、警察や検察の取調べに嘘の自白をしないように激励しました。また、警察官や検察官に、殺人事件ではなく、転落事故であることを説得しました。
店長死亡後は、警察の取調べが厳しくなりました。警察官が脅迫的に自白を迫る場面もありましたが、その都度、警察に抗議して、自白の強要をやめさせました。
その結果、会社員は、最後まで否認を続けられました。
そして、最終的に、嫌疑不十分を理由に不起訴処分となりました。
殺人罪で逮捕、勾留されて、不起訴処分になることは、めったにありません。私は、弁護人として、大きな成果を勝ち取ることができ、大変うれしく思いました。
○ 会社員の声。「最初に曾根崎署で殺人未遂罪で逮捕すると言われた時、びっくりして頭が真っ白になった。弁護士さんのお陰で、無実が明らかになり、本当に感謝しています」
離婚事件は近年増加の一途をたどっていますが、特に対応が難しいのは、離婚して親権を手放すことになる方の親と子どもの「面会交流」の問題です。
以前は「面接交渉」という言葉が一般的でしたが、ちょっとかた苦しい言葉のためか、最近は「面会交流」という言葉が主流となっており、平成23年の法改正で法律にも「面会及びその他の交流」という表現が加わりました(民法766条)。
最近私が担当したある離婚事件では、私は母親側の代理人でしたが、父親側は子どもの親権を手放すことにはしぶしぶ同意したものの、定期的な面会交流を強く求めていました。しかし母親は、子どもを父親に会わせることに強い抵抗感をもっていました。
結果的には、半年に1回の面会交流を行うこととし、また、1回目に限り、子どもたちが遊んでいる様子を父親が遠くから見守るだけにする、という、ちょっと異例の決着となりました。母親の言い分をかなり尊重してもらった結果ですが、父親の側も、子どものことを真剣に考える姿勢を示したためにこのような結果につながったといえます。
離婚して親権を手放した親が、離婚後も子どもと定期的に面会交流をすることは、子どもの成長にとって重要です。夫婦が離婚するときは、子どものために円滑に面会交流ができるよう配慮することが大切です。
もっとも、面会交流は、あくまで子どもの健全な成長に好ましいと考えられるからこそ認められるものですから、面会交流を行うことが子どもにとって大きな負担となるようなときは、無理に面会交流をすべきではないと思います。ある元家庭裁判所裁判官も、「強く反対する親権者の意思に反して面会交流を強行した結果、子どもの心に大きなダメージを与えてしまったケースがある」と指摘しています。
ところが、弁護士や家庭裁判所の調停委員の中には、「親(または子)には、面会交流を求める権利がある」と当然のように考えている人もおり、対応に苦労することがあります。
アメリカなどのように、離婚後も両方の親が共同で親権を持つのが原則とされているならば、面会交流を「親(または子)の権利」と構成することも可能でしょうが、離婚したときは一方の親のみが親権を持つとされている日本の法制度の上では、面会交流を控えるべき場面があることはやむを得ないところでしょう。
マンション管理組合から依頼された事件で、このたび、勝利判決を得ました。
事案の概要は以下のようなものです。新築のマンションが販売された際、売買契約書に「売り主が業者に委託してライフサポートというサービスを行う」 「売り主と業者の間で締結するライフサポート業務委託契約における売り主の地位をマンション管理組合が引き継ぐ」「ライフサポート契約は10年間解約でき ない」などとする条項が入っていました(紛れ込まされていたと言った方が適切かもしれません)。このサービスの内容については、健康診断や医療サービスな どがあるということでしたが、詳しくは分かりませんでした。マンション購入者は、売り主を信頼して売買契約書に署名・押印したのです。
ところが、その後開始されたサービスなるもの、月額61万円もの業務委託費を取りながら、2ヶ月に1度簡単な健康診断もしくはセミナーが行われる程 度のあまりにも杜撰なものだったのです。これではライフサポート業務委託契約書(マンション住民の知らないところで勝手に作られたいい加減なものですが) の内容さえ満たしていません。そこで管理組合はサービス主体との間で話し合いをしてサービスのきちんとした履行を求めたのですが、その後に至るも一向に サービス内容は改善されませんでした。
このような「サービス」で10年間合計7400万円もの業務委託費を取られてはたまりません。本来、本件のような契約(準委任契約)は当事者間の信 頼関係が維持されることを前提としているものですから、いつでも解除できるのが原則です(民法651条)。本件では「10年間解約できない」とした契約書 が作成されている点が気になりますが、永遠の契りを交わしたはずの結婚であっても離婚という制度が認められているではありませんか。このようなサービス契 約の解除など当然に認められてよいはずです。
ですから、管理組合は契約を解除した上で、業者に損害賠償請求の裁判を提起しました。これに対して相手方から は、解除は認められないので未払いの業務委託費を支払えと逆に訴えてきました(反訴)。
裁判の中では、相手方の主張が二転三転し、証人尋問では数々の矛盾点が明らかになるなど、デタラメなサービスぶりがはっきりしました。ですから、私 としては「いける」と踏んでいました。しかし、1審裁判官の考えは「10年間の契約をしたのだから仕方がない」というものだったようです。
1審判決は完全敗訴でした。自分を信頼し、依頼してくれた住民の皆さんが総額7400万円ものお金を支払わなければならないという重すぎる判断に、 目の前が真っ暗になり、一時は本当に眠れませんでした。しかも、追い打ちをかけるようにインターネット上のマンション掲示板に「弁護士を変えるべきだ」な どという意見が……。
しかし、一方に勝者がいれば他方に敗者があるのは世の常です。判決内容は決して説得的なものではありませんでしたので、「まだ控訴審がある」と気持ちを奮い立たせました。
控訴審では60頁の控訴理由書を書いて、1審判決を徹底的に批判しました。自分で言うのもなんですがこれはなかなかの力作で、これによって住民の皆 さんの信頼も回復することができたと思います。その控訴理由書がよかったのか、元々1審判決が無理筋だったのか、高裁裁判官の心証はこちらにとって大変に よいものでした。
控訴審判決では、契約の解除が認められ、債務不履行による損害賠償請求についても既払い額の4分の1の限度で認められました。
相手方は上告・上告受理申立をしてきたのですが、このたび上告棄却・上告不受理の決定が届き、4年に及ぶ紛争に決着が付きました。
それにしても、考えさせられるのは契約書に署名・押印することの重みです。マンション売買契約書に本件のような危険が潜んでいるとは、通常誰も思わ ないでしょう。しかし、契約社会においては「そんなことがあるとは思わなかった」という言い分をなかなか認めてはくれません(実は今回の裁判でも契約自体 無効の主張をしていたのですが、これは認められませんでした)。
今回のケースでは、実施されたサービスの内容が余りにも杜撰だった事から無事解決ができました。しかし、もう少しましなサービスが行われていたら ――形式的にはサービスの形が整っていたら――どうだったでしょうか? その「サービス」が対価には到底見合わないような内容のものだったとしても、契約 を打ち切ることは難しかったかもしれません。
契約書に署名・押印する際には、内容にしっかり目を通し、少しでも疑問に感じたら詳しい説明を求める、それでも納得がいかなければ弁護士などの専門家に意見を求める、といった慎重さが求められます。